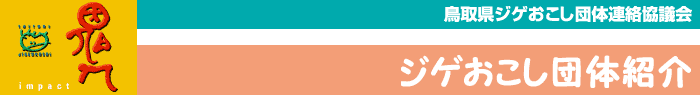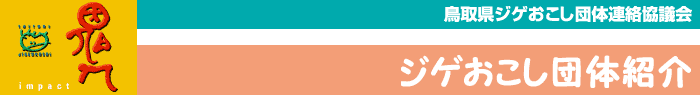所
在
市
町
村
|
活動団体の
名称・URL |
構成
人数 |
活動分類 |
活動内容 |
設立
年月 |
設立目的 |
連
絡
先
氏
名
|
米
子
市
|
米子がいな太鼓保存会 |
142人 |
芸術文化 |
年間出演約80回と国内外の太鼓交流を展開。創作活動にも力をいれ数々の曲を創作、近隣地域への作曲指導も行っている。 |
1975年
1月 |
米
子
市
には郷土の芸術が何もなかったため、唯一の郷土芸能の創設、伝承を目的として設立 |
佐
々
木
美
紀
|
米
子
市
|
ブックインとっとり実行委員会 |
18人 |
芸術文化 |
全国の地方出版物約500点を集め、県内4市をリレー展示して地方出版物を紹介。会場内での人気投票を基礎として地方出版文化功労賞を選び表彰。記念講演会を開催し県民と交流。 |
1985年 |
地方出版物に光をあてる。 |
古
瀬
美
保
子
|
倉
吉
市
|
倉吉まちづくり協議会 |
380人(内団体150) |
全般 |
市民行政が一体となりまちづくりに取り組む。研修会実践活動、他団体との交流、会報の発行(H13.4見直し検討中) |
1984年
4月 |
市民参加による「市民憲章」のめざすまちづくり実践活動をすすめること。(H13.4見直し検討中) |
小
谷
喜
寛
|
倉
吉
市
|
倉吉打吹ライオンズクラブ |
65人 |
福祉教育環境景観国際 |
玉川の浄化と美化運動活性化のため「くらよし打吹流しびな」実施、玉川清掃奉仕美化運動、一輪車大会の実施等による青少年育成等 |
1969年
11月 |
”我々は奉仕する”をモットーとし、『愛と指導で青少年をよりたくましく』をスローガンとしている。 |
小
谷
か
お
る
|
倉
吉
市
|
倉吉打吹太鼓振興会 |
110人19団体 |
芸術文化 |
倉吉打吹太鼓の振興と普及。市内の太鼓連を指導育成する傍ら、各種イベントへの参加を中心に活動し、異種の団体との交流も図る。 |
1989年
1月 |
倉吉打吹太鼓連を育成・運営し、倉吉打吹太鼓の普及を図り、演奏活動を通じて市民に夢と勇気を持たせ、まちづくりの活力を創出し倉吉市の文化振興に寄与する |
|
倉
吉
市
|
ロマンチック街道313
倉吉市中部地区協議会 |
50人 |
特産品イベント観光環境景観 |
国道313号線を活かした広域の地域おこしのための地域間交流、道路環境づくり等を実施。その他、これまでに絵はがき作成、ジャズコンサートツアー等を実施。 |
1991年
3月 |
国道313号線をロマンチック街道313と称し、名前にふさわしい街道づくりを通じて、地域振興と地域の活性化を図ることを目的とする。 |
前
田
六
仁
|
倉
吉
市
|
倉吉ニホンリスの会 |
200人 |
環境景観 |
急減するニホンリスの保全、生態研究、リスの里づくり。秋には子どもと恒例のドングリ拾い、リスのえさを確保するために、ひまわり、クルミ等を毎年植えている。 |
1991年
3月 |
鳥取県ではほとんど見られなくなったニホンリスを保護繁殖し、打吹公園内に放す。自然、動物、人の共生するまちをめざす。 |
松
尾
龍
平
|
倉
吉
市
|
みこしネット“風雅” |
70人 |
イベント |
浅草三社祭、打吹まつり等各種イベント参加の実践活動、他団体との交流、会報の発行 |
1994年
1月 |
お祭り大好きな女性が、みこしをかつぐことによって、仲間の輪、活動の場を広げ、まちの活性化を図るためひと肌もふた肌も脱ごう。 |
武
内
恵
子
|
倉
吉
市
|
くらしと住まいを考える会 |
22人 |
人材育成 |
高齢者、障害者のくらしを考える研修会等を実施。車イス体験、おむつ装着体験等・町を歩いて「やさしい町をつくり隊」冊子作製、写真入り・「介護保険でできる住宅改修」冊子作製(H12.12月) |
1991年
6月 |
住まいを考えることは、くらしを考えること、生き方、死に方を考えることだと思います。生活から住まいを考えてみよう。 |
山
田
満
寿
子
|
倉
吉
市
|
打吹童子ばやし振興協議会 |
協議会会員150名、団員28名 |
イベント芸術文化人材育成 |
打吹童子ばやしは、小学校2年〜6年生で構成する和太鼓と笛のグループです。毎週水曜日17:30〜19:00に倉吉市勤労青少年ホームで練習。各地のイベントで演奏し、倉吉の打吹天女伝説を普及、伝承。 |
1992年
10月 |
ふるさとに伝わる天女と童子の物語を「打吹童子ばやし」として、子どもたちの心のふるさとづくりを目的に、子どもたちのうきうきするお囃子の音で、「ふるさと自慢」として伝えていこうと活動。 |
村
田
速
実
|